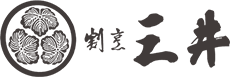節句の祝いに最適な和食とその由来

節句とは、日本の伝統的な季節の節目を祝う行事として子どもの成長や健康、家族の幸せを願う大切な機会です。
年間を通じていくつかの節句がありますが、特に有名なのが3月3日の「桃の節句(ひな祭り)」と5月5日の「端午の節句(こどもの日)」です。
これらの節句には、それぞれにふさわしい和食の料理が用意され、祝う風習が今も大切に受け継がれています。
桃の節句では、彩り豊かなちらし寿司や、はまぐりのお吸い物、甘酒などが定番メニューです。
ちらし寿司は、華やかな見た目が祝いの席にぴったりで、子どもの健やかな成長を願う気持ちが込められています。はまぐりのお吸い物は、一対の貝殻がぴったり合うことから「良縁」や「一生一人の人と添い遂げる」ことを象徴し、特に女の子の成長を祝うのにふさわしい料理とされています。甘酒は体を温める飲み物として親しまれ、健康祈願の意味もあります。
一方、端午の節句では、柏餅やちまきが有名です。
柏の葉は新芽が出るまで古い葉が落ちないことから「家系が絶えない」との意味が込められ、男の子の健やかな成長と家の繁栄を願う縁起物とされています。
ちまきには邪気を払うとされる歴史的なもので、魔除けの効果があると信じられてきました。
また、鯉のぼりにちなんで魚料理、特に鯛の塩焼きなどを食卓に並べる地域も多く、お祝いの席にふさわしい和食が用意されます。
節句の和食は、単なるごちそうではなく、家族の絆を深め、伝統文化を次世代に伝える貴重な時間をつくるものとして、料理に込められた意味や季節感を大切にしながら、子どもの成長を祝うひとときを、和やかに楽しんでみてはいかがでしょう。